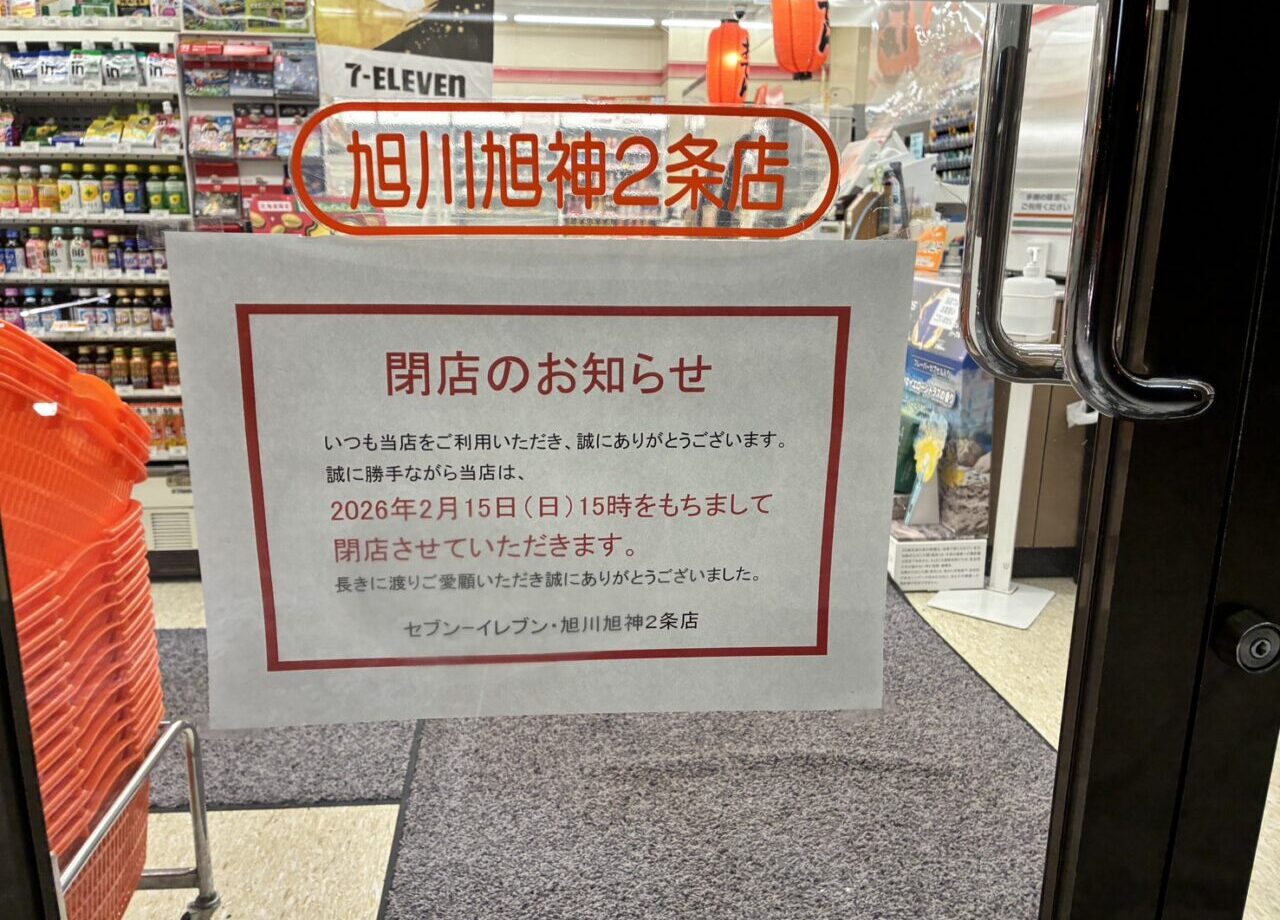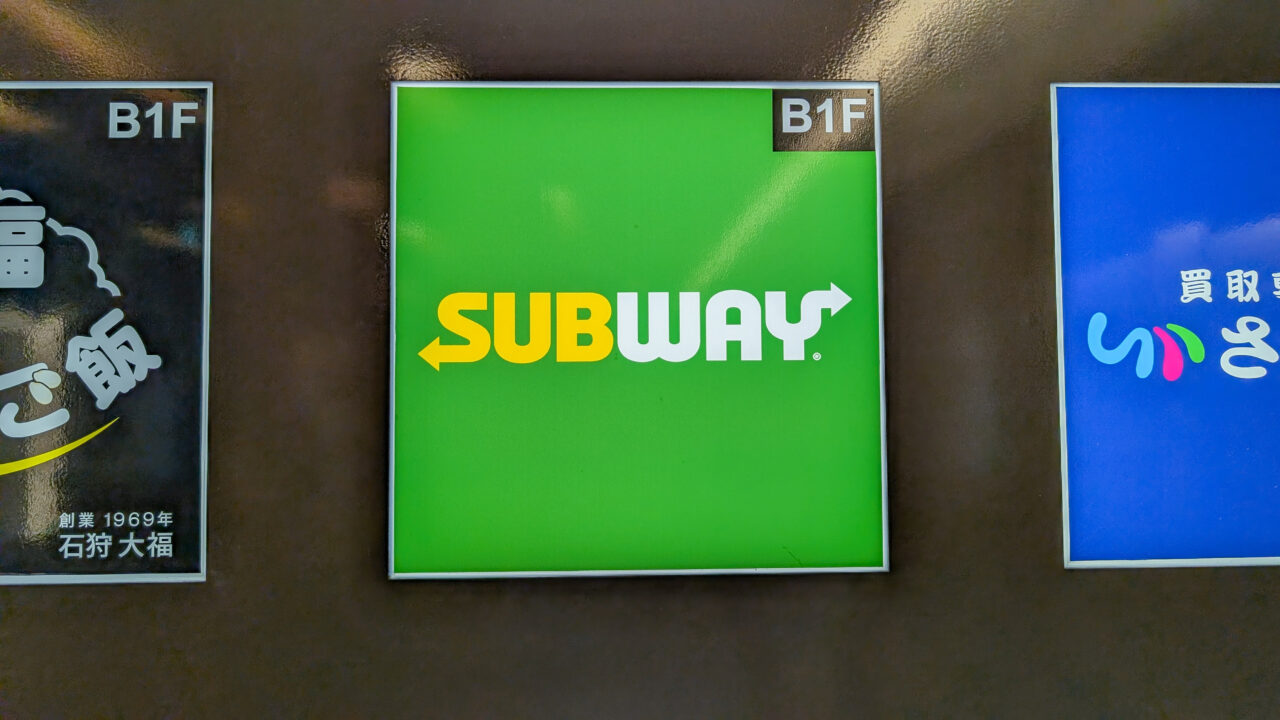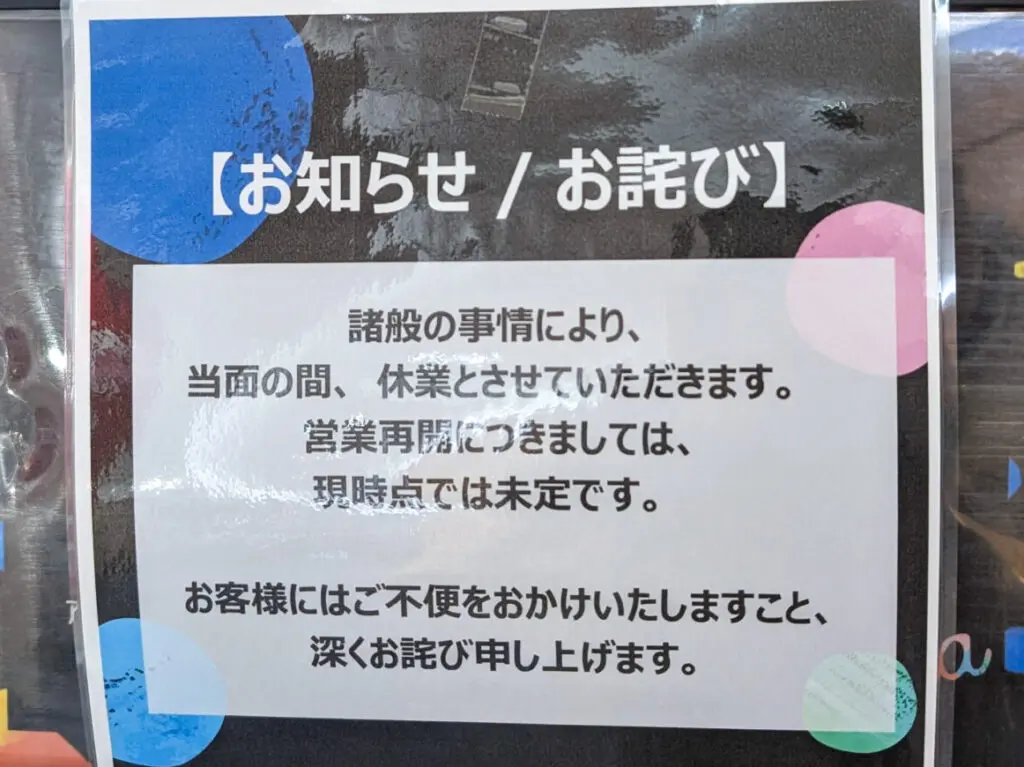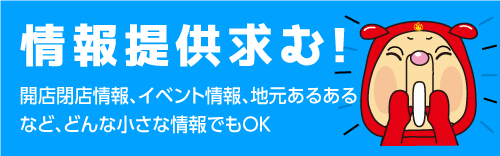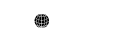【旭川市】神楽岡の地に鎮座し102年。上川神社には三度の移動の歴史あり。かつてはどこに鎮座していたかご存じですか?
1924年(大正13年)に神楽岡の地に遷宮した上川神社。2023年には鎮座100年を迎え、奉納行事などが行われました。みなさん、上川神社が神楽岡に鎮座するまで、何度か移動(奉遷)していることをご存じでしょうか。上川神社の移動は、旭川の街の発展と密接な関わりを持っています。
上川地方の開拓守護の神並びに旭川の鎮守として上川神社が誕生したのは1893年(明治26年)7月15日のことでした。その場所は旭川市史に「宮下通四丁目から七丁目に当る忠別川沿いの高台、通称義経台に、三百二十坪の土地を境内予定地として」と記載があり、現在の旭川駅に向かって右側一帯の通称義経台と呼ばれる丘に天照皇大神と書いた標木を建て祀ったのが起源となります。忠別川沿いには今も「古跡義経台」の碑が立っています。
また一条通には「義経台跡」の史跡表示板が立っており、この一帯はかつて丘陵地であり最初の上川神社が建てられたことが記されていました。上川神社が鎮座する前はアイヌの人々のチャシ(城砦)であり、悲恋話も伝わっているそうです。
さて通称「義経台」はどれくらいの高さがある丘だったのでしょうか。みなさん気になりませんか? 残念ながら記録には残っていないそうです。ただ、「土地は高燥であり、往来をはなれており、近所憚ることも無い所であつたので、忽ち青年連中の相撲場が出来、毎夜々々相撲でにぎわった」と旭川市史にあることからも、それほど高い丘ではなかったのかもしれませんね。
9尺4方(約2.7メートル)の神殿も造営し「上川神社」と称号も決まりましたが、1898年(明治31年)に移転が決定します。通称義経台に鎮座していたのは、およそ5年間でした。移転の理由は、旭川駅の建設が決まったからです。1896年(明治29年)より鉄道の敷設のため義経台の丘陵は削られ、忠別川側に埋められたと記録にありました。「旭川駅」の開業は上川神社の移転と同じく1898年のこととなります。
現在の宮下通7丁目一帯を見ても丘であることを物語る証は見当たりません。ただ一帯の地名が現在は宮下通であり、1898年(明治31年)の「上川郡旭川市街図」を見ると宮下町という表記が見られることや、旭川市史によれば1895年(明治28年)に、市街予定地に次の字を置くと記載されており、に通(かつてはい通・ろ通などいろはにほへとを通りの名称にしていました)から宮下町に変更となったことが記載されていました。上川神社の下という意味で名付けられたことがうかがえるとのことです。かつて神社がこの一帯に鎮座していたことを地名が物語っています。
旭川の発展には欠かせない鉄道の敷設ならびに駅舎の建設により、上川神社は移動を余儀なくされます。次なる鎮座の地は、旭川市民の皆さんには見慣れた場所です。旭川市役所を背にし道路を挟んだ向かいの6・7条通8丁目周辺に、1898年(明治31年)7月、社殿を造営し移動(奉遷)しています。敷地は5,200坪と言われており、義経台と比較すると広大な敷地を要していたようです。
上川神社にうかがったところ、6・7条通8丁目に鎮座していたのはわずか4年ということもあり、その当時の確たる記録はほとんど残っていないとのことでした。跡地に碑などもありません。ただこの時代に後々に「謎」となる出来事が起きていますが、それはまた次の機会に詳しくご案内したいと思います。
移動して早々に、またしても神社の移動が浮上します。1903年(明治36年)1月に正式に神社創立許可が下りることが決まり、今後、神社が鎮座する一帯は発展していくことが見込まれ、「五・六条通方面の発展を期せんとする一派(五条派)」と「宮下通の発達を計ろうとして同方面に移そうとする一派(宮下派)」が生じ、誘致合戦が起きたことが旭川市史に記載されています。両派の対立は激化し、旭川町長本田親美はこの事態を憂い調停を依頼しています。時には腕力沙汰となり「場内の集合者一同の総立ちなって入り乱れて乱闘し、警察官数名では制止できず」ともあり熾烈さが旭川市史に克明に記載されていました。
この誘致合戦の決着は、調停委員らの斡旋により和合の宴が催され、上川神社の祭典を挙行。後日氏子総代を選挙し、その後、「宮下通20丁目地先」を氏子総代らが選定し、1902年(明治35年)12月に上川神社は移動となり、翌1903年(明治36年)に創立が許可されました。乱闘騒ぎまで起こした両派は、その後、あと腐れなく氏子として神社を支えっていたのでしょうか?
三代目となる上川神社の場所は、現在の「宮下東宮公園」周辺とのことです。かつてはこの場所一帯はどんつきと言われ、行き止まりだったそうです。確かに地図を見ても宮下通23丁目周辺は道が入り組んでいますね。ここから「宮下通20丁目地先」は神社とともに発展していくことになります。
鳥居や社殿も造営し、時代は大正に入ったこともあり、写真が残されていました。おそらく例祭の日でしょうか。社殿の前でおみこしとともに映る大勢の子どもたちの姿はどこか誇らしげでもありますね。また境内には多くの人が集っています。
上川神社によると、写真はあるものの石柱や鳥居、社殿の正確な位置は不明とのことでした。上川神社には当時の図面が残されており、一帯は農耕地と住宅地に挟まれていました。1902年(明治35年)の登記の住所は「宮下」とあるものの、斜線が引かれ忠別太と訂正されており、まだ正式にはこの一帯の地名は忠別太であったことが分かります。
宮下時代は1924年までおよそ22年間、続きました。そして、3度目の移動が決定します。今から102年前の1924年(大正13年)6月6日、正式にはいまだに取りやめの沙汰が出ていない「上川離宮」計画の選定地であった神楽岡に上川神社が遷宮することが決まり、現在の場所に鎮座となりました。1924年と言えば、前年に関東大震災が発生しています。
それから102年が過ぎ、今年も7月20日から三日間「上川神社例祭」が開催されます。神輿は宮下東宮公園や6・7条通8丁目周辺などかつての上川神社があった場所にも渡ります。
上川神社の三度の移動を追うと、旭川の発展と上川神社が深く関わっていることがうかがえます。上川神社が鎮座していた場所を通った際は、みなさん、かつての神社の姿をぜひ想像してみてください。もしかすると神社跡に、みなさんの家が建っているかもしれませんね。
*上川神社さまに取材にご協力いただきました。また貴重な写真も撮影させていただき、ありがとうございました。
古跡 義経台&上川神社発祥之地はこちら。↓
旭川表示板「義経台跡」はこちら。↓
宮下東宮公園「上川神社址」はこちら。↓
上川神社はこちら。↓